終幕の半分
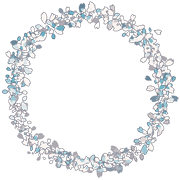
瀬見様におかれましては、日々の管理運営、誠にありがとうございました。迅速なご対応、細やかなお心尽くしに支えていただき、伸び伸びと活動に専念することができました。姫ぎみと騎士、身分違いのふたり、神話信仰に基づく忌みごと、最後に突きつけられる選択……と、大好きな要素しかない世界に産声をあげさせていただけましたこと。ご参加の皆様と共にキュクロスの地に生きられましたこと。すべてがこのうえない幸せでございました。
そして大好きなレイチェルさんとPL様、このたびは大変お世話になりまして、本当に本当にありがとうございました。安定して続けてくださったご活動に対して、こちらの不安定なレスペースでご負担をおかけしてしまい、加えて、なにかと先走っていたり、展開を強引に進めてしまったり、ミスもたびたびあり…と反省点をあげれば枚挙にいとまがなく…。至らぬPLに最後までお付き合いくださいましたこと、深くお礼申し上げます。終章〆レスの際にもあたたかなお気遣いをいただきまして、本当に感謝の念に堪えません。終わらないで…としくしく泣きながら最後の一文字を打ち終えたときの名残惜しさ、寂しさ…そしてなにより、こうして振り返りながら、どれほど言葉にしても足りないほどの幸福を腕いっぱいに抱えて、かけがえのない時間を過ごせたのは、お相手してくださいましたレイチェルさんPL様のお力があってこそのことでした。ありがとうございました!
「血は呪いに打ち勝つか」。レイチェルさん(“シェリル”呼びはPCの特権ということで、PLはこのままレイチェルさんと呼ばせてください…!)のプロフィールを拝見して、この出だしからぐっと引き込まれたのをよく覚えています。生まれながらの呪いに対して、ならばと剣をとってみせた双子。設定の妙は言うまでもなく、気心知れた姉妹の関係や、ぽんぽんっと軽やかに言葉を紡ぐいきいきとしたお姿……レイチェルさんのすべてに惹かれて、前のめりで愛を綴ったペアアンケートには、ジルベルトの目にはきっとまばゆい光のように映るかた、としたためておりました。圧倒的光…という印象は今も変わらないのですけれども、萎縮してしまうようなまぶしさではなく、絶えず降りそそぐ陽の光のあたたかさを持つおかたであった…としみじみ思い返しております。一国の姫ぎみとしての気品を備えていらっしゃって、けれど決して近寄りがたくはない、それどころか自然と引き寄せられるような、愛らしく気さくなお人柄。PL様の、かろやかで美しい筆致で描き出される息づかいが本当に素晴らしく…!好きだ……とどんどん惚れこんでゆく一方で、お相手するのがまるで騎士らしいところのない、こんなじめっとした男でよいのだろうかと、ぐるぐると模索を重ねる日々でした。ペアアンケートには、呪いを打ち払わんとする御手に力を添えてさしあげられたら…とも書いておりまして……振り返ってはしおしおとなってしまうのですが……できて……いましたでしょうか……。
願書でも少しお話しさせていただいたのですけれども、『half of breath』様では結末に至るまでの流れがあらかじめ明かされているということで、物語の最初から最後まで(よい意味で)苦しみ悩み抜くのだろうな、というような予想を立てていました。…が、期間を終えた今、振り返って、すべてがずっと葛藤のなかにあっただろうか…と考えると、それはまた少し違っていて。というのも、期間前半はレイチェルさんと日々を過ごせる幸せに、あっという間にずぶずぶずぶと沈みこんでしまいまして…。時々ふと先の展開を思い出して、「そうだった…」と我に返ることすらあったほどでした。そのぶん、やはり後半に進んでゆくにつれて、向き合わねばならない厳しいさだめに深く深く苦しみ悩んでのたうちまわることになったのですが、ここで言う苦しみや悩みはもちろん喜びと同義ですので、尻尾をぶんぶん振って庭を駆け回った、という意味に捉えていただければ…。レイチェルさんとPL様に、絶えず喜びを与えていただいた毎日だったなあ…と思い出に浸る今も幸せな心地でおります。輝ける宝物のような日々に、なにか少しでもお返しできていますことを願うばかりです。
最後にこの場をお借りしまして、少しだけ。ジルベルトを“ジル”と呼んでいたのは、レイチェルさんPL様のお言葉をお借りすると、「長く暗い夜の底に葬られてきた名もなき者たち」でした。PL様がエピローグで描いてくださったしあわせな未来の形、最高の結末を迎えた今となっては蛇足であるかな、と思うのと、何より、これから未来永劫“シェリル”さんだけの“ジル”です!と主張したい気持ちもあって、そんなこともあったんだな、くらいのふわっとした感じにおさめていただけましたら幸いでございます。
…と、なんとも締まらないご挨拶で恐縮ですが、改めまして、瀬見様、レイチェルさんとPL様、ご参加の皆様。このたびはありがとうございました!賜ったご縁に心よりお礼申し上げますと共に、皆様のこれからが幸多きものでありますよう、お祈りしております。
いいわ。もう。レイったら。わたしにな~~んにも、教えてくれないつもりなのね。(斯くして、ぷいとそっぽを向き、住まいのひとかどから封じの魔法にまもられた扉を抜け、ずんずんとはや足で出てきたのが先ほどのこと。[序章]
春を告げるコマドリの腹のような、灰色がかった青みのコート、ウエストコート、ブリーチズ。白い膝丈の絹靴下に覆われた男装の足もとも、見事に生えそろう芝の上へと踏み出した。[序章]
――……いいえ。無礼などとは。呼びかけたのは、こちらのほう。それでもあなたが気に病むなら、こうしましょう。……ゆるしますよ。ジルベルト。[序章]
ぱあっと、呼応してこちらも表情を明るくさせれば――膝をかかえていた腕をほどき、顔の前で、両の指先を押し合わせる。)まあ。まあっ! ……では、わたしたちは、同門の徒、ということになる?[序章]
(昨日には、貴婦人の装いに合わせ、およそ手首までの丈のレースの手袋に覆われていたであろう指先。深窓の姫君がもつ繊手にはありえぬ張り詰めた皮膚に、ふしくれだつ関節のかたちを、しかし双子のいずれも恥じたことはついぞなかった。われらが、わが、生のあかし。[序章]
……いいの……?(可否を問うような言いかたではなかった。おそれるのでもない。まず期待にも似たひかりがその瞳にあらわれて、みるみる、表情いっぱいにうれしげな笑みが広がってゆく。)もちろんよ。もちろん。きっと……おしゃべりをするよりたくさん、あなたを知ることができるわね。(先の会話を引いて、おのれはそんなふうに解釈をしていた。)[序章]
いちど深く呼吸し、まなざしを交わす。ふいの先ぶれに、くちびるには好戦的な笑みがおどった。)――のぞむところよ。[序章]
……ふッ!(薙いだ剣先に手ごたえはない。かろやかな跳躍。攻撃を繰り出すたび詰めていた息を吐き、返る刃を反動にまかせ背を反らすことで避けると、すぐさま肺へと空気を取り込む。全身をめぐる血のひとしずく、ひとしずくが、熱をもち掻き立てるようだ。ああ、これは、なんて、たのしい――。[序章]
双ツ首の、竜を討つのでは、ないわ。(彼にはなんの落ち度もない。だけれど、ほんの少しだけ、悲しげな、あるいは苦しげな吐露となってしまった。――半分の姫。それは王城のいたるところ、円柱の陰で、回廊の隅で、絶えずささやき交わされる噂。禁忌の秘めごと。)呪いを、そそぐの。わが血肉をもって、あかすのよ。「血は呪いに打ち勝つ」――と。(キュクロスは騎士の国だ。幼子らしい突飛な思いつきを、それでも信条にして息をしている。[序章]
そりゃあ……どうしてもあなたの気がとがめる、というなら、いまからでも着替えてくるわ。“町の娘さん”ふうに。(きっと。いまこのときも身にまとう、常の男装姿から。自信はないが、そのあたりは侍女の手にまかせよう。どちらがいい? と問いかけるよう、なかば強引に約束を取りつけたかもしれない騎士を前にして、首をかしげて振り仰ぐ。)[一章]
(上背をすぼめるように、とぼとぼと歩く。ごくはじめのころには、そんな新たな付き人の姿が――ああ姫さまは、今度はいったいなにを掘り起こして放り込んだのかしら? だの、いえいえ先日のあなたの声がけが、いささかきついように聞こえたのではなくって? だの、侍女たちの憶測をさまざま呼んでは、心配そうに様子を窺いたがるまなざしが、騎士と姫君を遠目より幾重にも取り巻いていたものだった。[一章]
ふふっ! なら、そうするわ。素敵ね。誘われたら、踊りの輪に入る……そのときは、あなたの手を引いて、一緒に飛び込んでも?(妹としてはややめずらしい、からかいじみた誘いの言葉。なにも無理強いをしようというのではないが、まずは反応を楽しんで、あわよくば、を狙うくらい。[一章]
だっ、だめ! ああ、びっくりした……。それは到底、ゆるしませんよ。(とは、いかにも主人らしく窘める口ぶりで。)もうっ。そこまでやわな足ではないのだし、それに――……、(そこで、ふと、内緒話をささやくように声をひそめる。いわく「片脚になってしまっては……“また”の機会に、やすやすとわたしに勝ちをゆずることになるけれど」?[一章]
――……ね、(「ねえさま」? 思いもよらぬ提案に驚いて、つい、うっかり歩みを止めてしまう。その場で急に立ち尽くし、)……わたしが。(王家の末という順のみならず、禁忌の双子としてもあとに産声を上げた。生まれてこのかたずっと妹。気がつけばおかしげな笑みが、ふいにこぼれる。)ふ、ふふ。では、そうしましょう。今日にかぎり、わたしのことはこれ以降、ねえさまと呼ぶように。“ジル”。[一章]
秘密ごとをまもる境界で彼を待たせ、ほどなくして現れるのは――実りゆたかなこがね色の袖つきの胴衣に、苔むす木陰にも似た深い緑のスカート。前には木綿のエプロンを提げて、開いた襟ぐりにはフィシューを入れ込むことで肌を隠し、防寒も兼ねている。耳上で左右に結い上げた髪は同じく、こがね色のボンネットのなかに収められていた。収穫祭では、花や実のついた枝を帽子や上着の胸もとに挿すそうで、ゆえに飾りは控えめに。さても“弟”と並べば、秋も深まる色合いだ。)さあ、いきましょう。(やや気恥ずかしさを誤魔化すよう促して、差し出される腕を待つ。)[一章]
とりどりの花たち。あちらの大ぶりは、はて秋ばらかダリアか。よりいっそう目立つのは、鶏冠のごとく燃え立つ花穂。あかあかと色づく野いばらの実も。めいめいが好きなものを、心ゆくまま。誰ぞの気持ちを和ませる――という意味では、夜会の華も、懐古にたゆたう使用人を、あるいは慰めていたのかもしれない。事実、末姫はなにも盛装を厭うているわけではないのだ、と知れわたったあの春以降、機会があれば、侍女たちはこぞってわが身を飾り立てたがったものである。そういう場への出席は格段に増えた。ゆえに。)[一章]
ジル、(ああ、なんて弱々しい声だろう。縋るようにその袖を引いては、相手のまなざしを受けたがった。これが片割れであったなら、うんざりしていたところで渡りに船とばかりに付き人へ託し、追い打ちのひとつやふたつ、かけることもできたのだが。)さっきの花かごはね、もちろん、勧めてもらったとおりに……自分のぶんを買おうとしていた、のだけれど。いまのお礼に、あなたにも、その、お花を――……贈っても、いい?(もとより、買い求めた花かごより一輪、“弟”に似合いの花を見繕うつもりであったのだ。しかしながら、唐突に吹き抜けた木枯らしに、いまはすっかり弱気になって。まずは、そんな問いかけを。)[一章]
持ち前の度胸と機転、記憶の共有でどうにか乗り切ろうにも、綻びの現れる場面というのは必ず出る。そこが弱い。お礼、と持ちかければ彼が困るのはわかっていた。けれども、こんなとき、わかっていて、あえて尋ねることしかできなくなってしまう。――なにか、かたちだけでも対価を差し出さなければ。もとの厚意を飛び越えて、どうしてか、そんな気持ちに駆られる強迫性。とりわけ、彼は秘密を知らない。付き人として陰に日向に添わせるくせ、いまだなんの事情も明かされずに。)[一章]
選んだ花かごは、はじめに勧めてもらった種類の花に、早咲きの三色すみれが加えられているもの。ひと花に双つの彩が混ざるようなら避けるべきだが、これは違う。控えめな野趣が彼そのひとを思わせて、ひと目見たときから決めていた。[一章]
ふふっ。“約束”よ、ジル。いきましょう!(宣言のとおりに、手を引いて。またも内緒話をささやくよう、声をひそめる。)大丈夫よ。わたしたち……あれだけ、剣をとって舞ったんだもの。心配いらないわ。なあんにも、ね。[一章]
……ふふっ。みんなで……ひとつの大きな輪になって、踊るのね。老いも若きも、生まれや立場さえも飛び越えて……ここでは誰もがひとしく、母なる大地のいとし子なのだわ。(およそひとが治める世のはじまり、はるかいにしえの、身分の区別もないころには、ただしく“そう”であっただろう人びとの営み。この場に片割れの手も引いて加われたなら、どんなにか、さらにすばらしかったことだろう。[一章]
ええ。決めたわ。また、あなたを――“ジル”と、そう、呼べますように。(たぶん声に出す必要はないのだろうが、願いを告ぐ先は空ではないのでこれでいい。)[一章]
――飾って半日も歩けばすっかり萎れてしまう祝福のあかしは、色が褪せる前に城の自室で清潔な布に挟み、重しを乗せて押し花に。そういう、大いに楽しんだ秋の日のこと。)[一章]
憂慮はない。万が一にも魔物が馬車を食い破り、乗り込んできた場合に迎撃する用意こそあるものの、いまはただ、本職の者に任せて待つがいちばんの得策。礼装のペティコートの下に忍ばせた、お守り代わりの短剣のかたちを確かめるよう布地の上から掌を当てて。まぶたを伏せては、いつもとなんら変わりのない彼の様子を思い返していた。)……心配ないわ。キュクロスの騎士はみな、つわものぞろいだもの。(隣へのはげましか、みずからへの言い聞かせか。やがてふたたびの静寂が戻るまで、祈るような気持ちで息を詰める。)[二章]
傷薬には、余裕があります。手当ての布も。すべての難が去った……というわけではないでしょうから、可能な範囲で魔法は温存して。ですが、使うべきときには使ってください。少し……我慢を、させますね。(こうして畏まった口調に戻るのは、これが公務であるからだ。[二章]
へいきよ。洗い清めれば、ちゃんと落ちるわ。(相手がなにをためらうのかわかるから、念押しのように畳みかけた。これはなんだかんだ、最終的には受けいれてくれるときの反応である。[二章]
…………ありがとう。たしかに、そういえば、そう……“レイ”が、泥んこになって戻ってきた日があったわ。見るなりみんな悲鳴を上げて、ああ、その日の……。(出立後の馬車のなか、背もたれに身をあずけてはぼんやりと、ふたりで答え合わせに勤しんでいた。魔法で封じられた王城のひとかどが、ひときわの騒がしさにつつまれた一日のこと。ようやくの心当たりに思い至れば、ため息を吐いてほほ笑もう。落ちない染みを誤魔化すように。[二章]
もちろん。なんなら……差し上げてもいいくらいだけれど、……ふふ。明らかに女性ものの意匠だから、ジルには使いにくいかもしれないわね。(レースでぐるりと一周縁どられた、女物のハンカチーフ。おのれのイニシャルは当然、なにか紋章が縫いとられているわけではないものの、見るひとが見れば、誰ぞより贈られたひと布であるとひと目で知れる。そう、おかしげに振り仰いではからかうように。[二章]
(町の子どもたちは屈託なく、物怖じをしない。芦毛のまわりにわらわらと集まり、飛び跳ねるさまはいかにもほほ笑ましい光景であったが――王家の末子という生まれからか、こうも大勢の年少の相手に囲まれるという経験がほとんどなかったので、馬上からではあるものの、どこかおっかなびっくり腰が引け、さも、たおやかな姫君のごとくほほ笑むことしかできなかった。しかし、無邪気な幼い手に袖を引っ張られ、脚をつつかれ、されるがままになっている付き人の姿にはおかしげな笑みを誘われて、いくらか自然にこう述べることもできただろう。「……町長のお屋敷に、王都みやげのお菓子があるから、さあ。みんな、はやい者勝ちよ」![二章]
わっと駆け出す賑やかさを、かたわらの青年と目くばせをしながら見送れば――そののちは、すぐ後ろで手綱をとる両腕のあいだから、ひょっこり顔を覗かせてはのどかな眺めを堪能して。)[二章]
(「そばに居てね」。目を合わせぬままに言い添えよう。――乳の飲みが悪く、そのあとも、なかなかうまく草が食めずに身体が育たなかった仔羊。あるいは、もはや次代を残せぬほど老いた羊や、そのほかにも。けして数は多くないが、たしかに選り分けられ、間引かれてゆく家畜たち。まだ若い少年に経験を積ませるのだろう。ひと思いにやれ、苦しませるな、と助言が聞こえた。陽光を受ける刃。皮や肉を断つ音、短い今際のひと鳴きも、ここまで届く。)……群れにそぐわない、適さないからといって、羊も、甘んじて“それ”を受けるわけじゃあない……。だけれど、そうして、めぐってゆくのだわ。(暴れ、痙攣していた四肢。いつの間にか爪の先が白むほど、防寒の手袋を外した掌を、拳にして握りしめていた。)[二章]
そうして、めぐらせてゆけるのが、ひと……、(そっくり復唱し、こちらを覗き込む、凪いだ湖面のまなざしを静かに見仰ごう。ああ知っている、と、ふいに感じた。天命のなすがまま、わが身をゆだねるのではなく、剣をとることを選んだ幼き日。なにかを思い出したような一点のひかりが、おのれの瞳に息を吹き込むごとく、みるみる常の様相を取り戻させて、)生きようと伸ばされる手を……誰ひとり、離さぬため……。(いちど、まぶしげに目を細めたのちにほほ笑んだ。)ジル。あなたは、――そういう騎士に、なる?(志のなんたるかを問うたのではない。どちらかといえば、そうであったらうれしい、くらいのささやかな胸うち。)わたしにも、できるかしら……。(おのが定め。至上の命題。めずらしく、弱音じみた世迷いごとになる。)[二章]
(吹く風に、かすかに冬のきざしがある。あたりがすっかり雪と氷に閉ざされて、ただひたすらに春の訪れを待ちわびる季節。――王領の羊は、彼らのたゆまぬ努力によって秋に新たな命を産むものもあるが、その多くはいままさに胎に仔をかかえ、いまだ冬の気配も色濃く残る春先に、つぎつぎ産声を上げるのだという。)すべての息づかいが絶えたような、冬の、そんなしじまのうちからでも……生まれてくる命が、ある……。(たしかにお産が近いのだろう。少しばかり荒い息を吐く母羊の背を、気づかうよう、障りにならない範囲で撫でさせてもらいつつ。)きっと、よい仔を産んでね。(命の誕生とは、すべからく、この世の春を予感させるのだ。啓示にも似た心地に打たれながら、しばらく身をまかせていた。――それはどうしてか、救いのようにも思えたから。)[二章]
わた、くし……の、……婚、約……?(ああ、まさしく天が落ちてきたか。まなこをそのかぎりに瞠り、ただそれだけを絶え絶えに問い返した末姫に、いらえる是は祝福に満ちて、あたたかい。詳細を引き継いだ大臣いわく――相手は隣国の王家筋。齢もさして離れておらず、なにより、女人の身で剣をとることに好意的で、たいそうご興味を示されているそうな。「かなうならいちど“手合わせをしたい”と……そう、書簡でおっしゃっていましたよ」。継母たる王妃の、心から安堵したような、うれしげな声音。[三章]
冬を間近に、春の日よりは水気が抜けていささか強張ったような、ごわつく蔦の肌ざわり。幾重にもつるが巻きつき繁る旺盛さは――そういえば、古来より、夫婦や家族を結びつける縁起物。[三章]
――……もう、“ジル”とも、呼べなくなる?(婚前の淑女である。わざわざ確認をするまでもないことだ。けれど、)こうして……ひとつ、ひとつ……手を、離していかないといけないのね……。(春の、小姓然としたなりとは異なる姫君の姿で、膝をかかえるようしゃがみ込む。[三章]
胸のうちで、嵐が吹き荒れているようだ。ひどい誘惑に駆られる。燭台から手燭へともし火を移すように、焦がれるに似た熱が、喉もとまでせり上がりかけて、そして、)~~~~ッ、(寸でのところでそれを呑み下しては、その代わり、彼のほうまでその身はんぶん、上肢ごと差し伸べてくずおれるよう、この膝をついてでも相手の膝上の拳をとりたがった。さも追いすがり、慈悲を乞うかのごとく。)ええ。ええ……憶えているわ。……わたし、どうして、そんなによくしてくれるのだろうとたまらなくなって、それでも。たしかに、うれしかった。うれしかったの。(忘れはしない。ひとつひとつを区切りながら言葉にして、やはり、涙ぐむことなくほほ笑もう。)[三章]
いまはまだ、この身の振りかたすらもわからないけれど、顔を上げて、背筋もしゃんと伸ばしていよう。あなたの前では。)[三章]
“わたし”の心の代わりに。(そばに置いて。忘れないで。想っていて。そんな希求が、たしかに透けた。「なにも得物の柄にくくりつけろ、というのではないわ」。冗談めかすその補足を、上手に楽しげに、口にできていればよかったが。)[三章]
――……いい、なあ……。(熾火の熱に浮かされて、気がつけばうわ言めく吐露が口をついていた。それは、家庭を築くことのできる相手に対してか、それともその妻となるひとに対してか、そのいとし子にか。)い、まの……わすれ……、(て、と続くはずの言葉。あわてふためく全身が、あつい。)[三章]
ああ……、(万感のため息がこぼれ落ちた。)……そう、できたら……どんなに、いいか……!(茜さす夕陽が、すべての境目をぼかしてゆく。わたしは誰。あなたは誰。つい先ほどたしかに呑み下したはずの熱が、ふたたび喉もとをせり上がる。――告げてしまえ、と、耳朶の裏で蛇がささやいた。甘言は、正面ではない横や、斜め後ろからそそのかすのがいちばんよい。視界を塞ぐも同じこと。困ったことに、“わたし”にはこたえられてしまうのだった。ああ、だって、嫁ぐのはこの身じゃあない。なのに。)~~~~ッ、……でき、ない……。(身体の中心から、ずたずたに引き裂かれてゆくようだ。言葉とは裏腹に、指先はたまらず騎士のサーコートにしがみつく。いつしか、覆いの内側よりあとから、あとから、涙があふれてしたたっていた。)だって、わたし……まだ、呪いを、そそげていない……![三章]
束の間、想像した。忌み子としての生の終わり、ただひとつ、たしかに呼べる名があるということ。)ふふっ。そのとき、かりに――……しわくちゃの、おばあさんに……なっていても?(きっと返るいらえを期待して、楽しげに、うれしげに声をはずませて。)ありがとう。約束するわ。そのときにはきっと……“あなた”を、呼ぶわね。(どんな守り石より助けとなる。握りしめるようほほ笑んで、たしかにそう頷いた。わがキュクロスをまもる霊峰の中腹、神殿、と称せるかもわからぬ人里離れた石窟での遁世の果て。その臨終の間際、皺枯れた指先をやさしく掬い上げる騎士の手を夢想する。愚かでも。この先も生きてゆけると、そう思った。)[三章]
(「あなたを、誇りに思います」。いましがた落ち着き、引っ込んだはずの涙の勢いがぶり返し、みるみるうちに視界がにじんでゆく。しかし、うまく伝えられたらいい。こたび降るのは、けして、悲しみゆえの雨ではないと。ほほ笑みを交わし、ふたり、糸にする前の毛束を、たがいの指先をつかって撚りあわせるような夢語りをしよう。[三章]
さっきみたいに、じかにお目にかかることは、そうそうないのだけれど……そういえば、昔、わたし……が、剣をとると決めたとき。父上が、たいそうよろこんでくださったと聞いているわ。でもね、兄上いわく……そのときは感極まるように、涙ぐんでもいらしたんですって。だから、もしかすると、ちょっぴり涙もろいかた、なのか、も……、(語尾へ向かうにつれて勢いがしぼんだのは、あまりに子どもじみた当てずっぽうだという自覚がさすがにあったからだ。ほんのりと、恥ずかしがるよう目もとを染めて。)ただ……これはまた、別のときの話なのだけれど。お兄さまがね、「玉座とは孤独なものだ」と、そうおっしゃって。……わたしには、国を治めるむずかしさは想像もつかないのだけれど、それでも、もし、かりにお父さまが涙もろくてさみしがりなかただったと、したら。ううん、しなくても。……お母さまを亡くしたあと、継母上が来てくださってよかったと、思う。[三章]
どんな理由があっても、なくても。わたし、あなたが――……“レイチェル”の騎士で、よかった。心の底から、誇りに思うわ。[三章]
だって……だってね、わたしには――……無理、なんだもの。(およそ消え入りそうな告解になにか察するものがあったのか、片割れの顔つきがふと、変わる。)――約束、したのよ。わが身をもって、心に勝利のあかしを打ち立てる……そんな日をいつか迎えられたなら、そのときには必ず、あのひとを呼ぶと。(今度こそ、伸ばされる手をとり、離れない。それがたとえば、この生涯の終わりにみる幸せな夢でも。半身とかたく抱きしめ合い、いまぞ誓おう。)だから、わたしとも約束をして。信じていて。いずこへと分かたれようと、血は、呪いに打ち勝つと。わたしたちの、剣をとるこの“手”は……たしかにそれをあかすことができるのだと。(忘れないで。想っていて。離れても。そんな希求が、たしかに透けた。涙に濡れた雨空の瞳が、たがいにたがいを映し込む。呪文で刻むまでもない。わたしたちは、こうして生きてゆく。)[四章]
――なれば王よ、われらは“時”が来るのを待ちましょう。罪をあがなう羊の、血が呪われ、穢れているというのなら、ゆえにこそ――そそいだのちに還さねば。折しも、物心がついた末姫たちは、誰に説かれるでもなく剣をとる。なんのめぐりあわせか。さてもキュクロスは騎士の国。王城の中枢は、妙なるこの因果にいたく感じ入ったようであった。これで、まことの円環に生まれたひずみは正される。双子の罪は清められ、ふたりはひとり、完全体に戻るのだと。これが、末の姫君“レイチェル”に、剣をとることがゆるされていた、もうひとつの理由。[四章]
(さて。キュクロスの古語に、こんな数詞がある。いち、を表すウーヌス。そこから、のちに続く言葉に合わせて末尾が変わり、そのうちのひとつが、ウーナ。そこから転じて“ユナ”。ゆいいつの、を示す品詞であった。そう。王家の末娘はひとりだけ。そして、罪をあがなう羊もまた、ひとりだけだ。[四章]
夜半に吹きすさぶ風はつめたく、生ける命の熱を奪い、凍えさせようとするかのよう。じきに、すべての息づかいはしじまに絶えるのだ、と思った。)[四章]
あたたかなぬくもりが、おののくこの手ごと、握りしめて言う。「わたしが行くわ」。符牒めいたそれにたしかな察しがついているわけでもないだろうに、そう言い張る片割れの、どこか怒りをあらわにする顔つきを前にして、ようやく少し笑えた気がした。)…………ふふっ。……だめよ。これだけは、“わたし”が。(独り占めしたがる子どもじみた欲を覗かせて、半身にはこう乞おう。)代わりに、支度を手伝って。レイ。ね、おねがい。[終章]
鏡台に腰を下ろし、姉の手ずから髪を梳いて結ってもらった。とくべつな髪型ではなにもない、変わり映えのしない男装姿。「介添人としてなら、ついていっても構わないでしょう?」――まるで、これから妹が、決闘に臨むとでも言いたげな食い下がりよう。腰に佩いた細剣の柄を撫ぜ、ちょっぴりおかしげにほほ笑んだ。)いいえ。わたしの愛しいおてんばさん。……どうか、お部屋で大人しくしていてね。(ついと背伸びをして、その額に口づけを捧ぐ。[終章]
(ほんとうは、「わからない」ではないのかもしれない。ああ、それでも。ほほ笑みを刷いて息を吸う。)――……愚かなるキュクロスの王よ。考えはしなかったか。おまえの迷いが、この国に、また新たな呪いを生むのだと!(朗々と張り上げる声は、彼というより宙へと向かった。外套を脱ぎ捨て、抜剣する。晴れ晴れ、と喩えるにはほど遠い、いまにも雨の降り出しそうな曇り空。束の間ゆがめてすぐ戻そう。)さあ。ダニエリの子、ジルベルト。(抜きなさい、と言外に命じて。)あなたは、その剣で……(無粋な観客の目から逃れるには、おそらく、そう、)……双ツ首の、竜を討つのかしら?[終章]
――“わたし”の生は、この国の、長く暗い夜の底に葬られてきた名もなき者たちの、連綿と続く円環の果て。それがわかると、死びとめく顔つきがふと、変わった。瞳にもまた、かすかに一点のひかりが戻ろう。たとえば、亡霊に足をとられて闇へ引きずり込まれるのではない。忘れないで。思い出して。この肩を、背を、さも励ますように軽く叩いては撫ぜてゆくあたたかさを、たしかにあずかる気がしたのだった。だから。)[終章]
――……“だから”、――そう。“めぐらせて”ゆけるのが、ひと、なのね……。(輝かしいのは、なにも、去りし春の日にかぎった話ではない。王領の端で迎えた秋の暮れ。あの牧地で聞いた言葉を、ようやく余さず受けとることができた気がして、こんなときなのにうれしかった。回想する。幼き日、長兄はこうも説いた。国に尽くし、民に尽くし、よき代を築けば、人心はおのずとついてくると。時の王妃が双ツ子を孕んだ大騒ぎの折には、すでに物心のついていた年長の王子王女たち。建国神話に深く根ざし、それを頼みとする権威のあやうさをいちはやくその肌で感じていたのは、彼ら彼女らであったのかもしれない。繰り返すばかりが円環ではないのだ。すべての息づかいを絶やさんとする、冬の、夜の底からでも、たしかに生まれきたる命がある。)[終章]
思い出したわ。ううん……忘れたことなんて、なかったはずなのだけれど……あらためて。わたしが、わたしたちが、はじめて剣をとった日のこと。(血に宿る呪い。双ツ首の竜が今際に吐いた息の緒よ。ぐっと身を沈ませ、地を蹴る反動で、すばしっこく駆けてゆく。あなたのもとまで。)誰のゆるしも、いらない。われら“レイチェル”はふたりでひとり、ただ、剣とともに生きてゆこうと!(斬り崩さず、受け流さず――同じ力で拮抗させようというのなら、あとは純粋な得物のつくりの勝負になる。すぐそばで、亀裂の走る音が聞こえた。騎士の長剣がもろともにこの首を落とすがはやいか、)生きようとしたの。――……ジル。わたし、ね……、(折れる細剣から手を離して、彼の懐まで飛び込むがはやいか。ささやくような睦言が、くちびるを震わせる。)[終章]
……今宵をかぎりに、とわのお別れをいたします。……あがないの羊、は、(そこで宣言は掠れて震えるが、続きを紡ぐことを止めはしない。)ひずみなき真円の理を外れ、ただ、名もなき者のひとりとなり、この国の、夜の底へとまいりましょう。それは……あなたがたの言うところの「大地へ還す」と、ほとんど同義なのではありませんか。(十七年前、父王を口ぐるまに乗せた側近を笑えぬと、ほんの少しだけおかしく思う。円環より外れた者は、この国では存在しない亡霊となるのだ。ふたりの末姫が、その存在を秘され続けたのと同様に。)ですから、いまぞ――……わが身のあかしを、ここにおかえしいたします。(そう口にするやいなや、片膝をついては足もとの柄を拾い上げ、後ろ手におのが結い髪へと刃を当てた。布を断つような音がして、こうべがすっかり軽くなる。宝飾のあしらわれた細剣のこしらえごと、それは、呼応するよう現れた魔法陣の上、まるで焚べられるように消えてゆき――)[終章]
だから、呼んでもらうなら……だけれど、あのね。もうひとつ新しい音をつけ加えようと、いま思ったわ。あなたの名前から、ひとつ音をもらって、(白い手巾の結ばれたほうの荷袋と、外套を差し出し、緊張したあらたまった顔で。)――……「シェリル」と、どうか……そう、呼んで。(きょうだいでは、“ねえさま”ではない、あなたの。ゆいいつを乞う。)[終章]
(産声を上げたゆいいつの名を呼ばれて、はじめに胸にきざした想いはなんだったか。手巾にくちびるを寄せるさまにも、はっとしたのちに目もとを染めて、)「少しだけ」?(と、からかいと、恥じらいのはざまにたゆたう復唱を落としたのだった。)[終章]
それでもあなたが気に病むなら、こうしましょう。……ゆるしますよ。ジルベルト。(まなざしは愛おしげに。)[終章]
たがいの頬がひたと触れ合う、ふたりだけの、はざまの“世界”。これより未来に多くの人びとと出会い、別れ、それぞれがあまたのえにしを手にする掌のうちに、ああ――しかしながら、ひと筋のひかりが差す前の、その、ほんの、二度とは戻らぬ払暁のあわいに。)――……ゆるすわ。(身じろぎの代わり、つのる思慕とともに、頬や鼻筋をすり寄せたがった。)と、いうより……もっと言うと、ゆるす、ゆるさない、の話では、なくって、(愛おしさに溺れかけながら、あえぐように息を吸えば、)どうか、知ってね。ジル。ゆいいつのあなた。わたしも、また……同じように、どれだけ、あなたをのぞんで……焦がれているか。[終章]
ジル。あの、ね。わたしね――……、(外套の内側で、ぬくもりを分かち合うよう寄り添って、鼓動に耳をかたむけていた。そうして、いくらか夢心地の口ぶりで語りはじめる、黄昏に覚えた羨望のこと。――いつか生まれるかわいい子に、おまえの父はかつて王城で姫君にお仕えしていたのだ、と昔話をひも解くとき。ちっとも信じるそぶりのないいとし子に、あなたはどんな顔を見せるだろう。そこへわたしは、お茶でも運んで、おかしげに笑ってとりなすのだ。それもまた、えがく未来図のうちのひとつ。わたしたちは、そうして生きてゆく。)[終章]
(幸いあれ)[エピローグ]
これより先は、ただひとりのためだけにゆく道ではない。多くの人びとと出会い、ときにはその手をとり、心を交わし、やがて別れを繰り返す。あまたのえにしを胸にいだく旅路のうち――たしかにあなたに、あなただけに、いつとて焦がれてのぞむ心があるということ。わたしを“最愛”と呼んでくれるあなたもまた、わたしのゆいいつ、わたしの最愛。ひとがなにかを欠いて生まれるのなら、たといそのうろを埋められずとも、つめたい夜の底で寄り添い、ぬくもりを分かち合うのは、あなたを措いてほかにない。)ジル。(ひかり輝く誓い、誇りの名よ。そばに居てくれるから、どんな困難にだって立ち向かえる。)[エピローグ]
……ふふ。これでもね、腕にはちょっぴり覚えがあるのよ。――まあっ。いいわ。よろこんで、お相手つかまつりましょう。見くびると痛い目を見ると思うのだけれど、(かかっていらっしゃい。幼き日、王城ですぐ上の兄君たちとそうしたように。――その、ささやかな勝負がひょんなことから白熱するあまり、山羊たちのお産がはじまったと、小屋から大声で呼ばれるまで気がつかなかったことは、それから笑い話として、しばらくのあいだの語り草となるだろう。いずれ“彼”の耳まで入るころには、だいぶん恥ずかしがっては、小さく縮こまっていたはずだ。いまだ冬の気配も色濃く残る春先に、つぎつぎ上がる産声たち。生ける命の熱を抱いて、その重みを腕に沁み込ませる。これから幾度となく手を伸べる、これが、はじまり。)[エピローグ]
知っている。ほんとうは、老いも若きも、生まれや立場さえも飛び越えて、誰もがひとしく、母なる大地のいとし子なのだと。おのれの代かぎりで遂げられるような話では、到底ない。なんの隔たりもなく、みなが春の陽ざしを当たり前に享受することのかなう日は、いまはまだ、はるかに遠い果てのこと。されど――それを“めぐらせて”ゆけるのが、われらひとであるならば、)さあ、いきましょう!(往きましょう。生きましょう。命のかぎり、あなたとともに。いつかに見た、ひかり降る町をはしゃいで駆けてゆく幼いきょうだい。彼ら彼女らが、双ツ子であろうと同じく。ひとの身はやがて朽ちるが、その想いは、言葉は、繋いで継いでゆくなら千年も残る。それもまた、円環のひとつだ。めぐりめぐる、これは名もなきおとぎ話。)[エピローグ]
生きようと伸ばされる手を……誰ひとり、離さぬために……。