終幕の半分
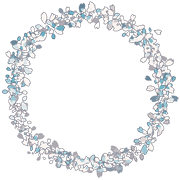
瀬見さま、参加者のみなさま、たいへんおつかれさまでした。真円を戴く国、キュクロスで、キャラクターのひとりとして物語のひとつの結びまで駆け抜けられましたこと、ほんとうにうれしく、しあわせな気持ちでいっぱいです。あらためまして、期間中はたいへんお世話になりました。レイチェルPLです。
思い返せば……サイトの導入にてひも解かれる世界観のはじまりから、ぐっと心をつかまれて、夢中で願書を書き上げました秋のはじまり。現実世界の時の流れとともに、物語のなかの季節も進みまして、いまは年の瀬も迫ろうという今日このごろですが……ほんとうに、かなしくも、いとおしい世界のうちで息をさせていただいたなあと、振り返ってはいまなお、しみじみと噛みしめる毎日です。世界の根底に、さもとぐろを巻くようにして横たわる、双ツ首の竜と、それを打ち倒した騎士の物語。いわゆる竜退治(あるいは竜殺し)というのは、神話のような伝説から民間伝承にいたるまで、古今東西、あらゆるところで語り継がれてきたお話のひとつですが、竜と騎士、という組み合わせも、西洋ファンタジーらしい“ロマン”をつよくつよく感じさせる、たいへんに興味深いテーマでした。心くすぐる世界観の、その枠組みをご用意くださった瀬見さまに、あつく感謝を申し上げますとともに、こちらにゆだねて見守ってくださる、あたたかなバトンの託しかたのおかげで、もうほんとうに、のびのびと、なんとも楽しく想像の翼を羽ばたかせることができたのだと感じています。期間中は本編に集中するあまり、壁打ちというものをうまく活用できなかった参加者ですので、ここで、あらためてお礼をお伝えさせてください。まことにありがとうございました。お世話になりました。「はんぶん」の世界で、キャラクターたちの想いを感じながら過ごせましたこと、心の底から楽しかったです。
もとが建国神話として謳われる騎士の血筋から興った王国ですから、この国でその象徴である「剣」をとるということは、相応の意味をもって受けとめられる行いなのではないかな……と考えたときに、ふと思いついたのが、剣をとる王家の末の姫君、というイメージでした。ここ百年ほどは内政も外交も安定し、現国王の治世にも不穏なところが(少なくとも表面上は)ないことから、キュクロスの人びとのあいだで長い時間をかけて醸成されてきた、ときにいにしえの代にすら通ずる空気……のようなものにも触れられるのではないかと考えたからです。こういう、創作のなかで国のたどってきた歴史に思いを馳せるというのは、個人的にほんとうに楽しい考察で、これも瀬見さまの奥行きの深いワールドセットによるものであると確信しておりますが、物語のなかでお相手さまと言葉を交わしてゆくうちに、どんどん、このふたりらしい「キュクロス」の姿がかたちづくられ、呼吸をはじめてゆく。その瞬間に立ち会うことがかなったのは、いちキャラレスラーとして、また創作にたずさわる者としても、たいへんにしあわせなことでした。
そして、多大なるお力添えをいただき、物語の結びまでをともに駆け抜けてくださいました、ジルベルトさんとそのPLさま。
ほんとうに、どこからお礼を申し上げればよいのか……。たくさんのお心づかいを頂戴し、気持ちと言葉をていねいに通わせながら駆け抜けてきた充実の期間中でしたので、本編を結び終えました現在、すでにとってもとってもさみしくてたまりません。とはいえ、どこかにやり残したことや未練がある、というわけではちっともなく。序章から終章、エピローグにいたるまで、たがいの胸のうちに触れながら、涙が出るほどいとおしい物語のひとくさりを無事に紡ぎきることがかないましたこと、まことに光栄で、なによりしあわせなことでした。
ひとつひとつのラブコールやメッセージなどについては、のちの「抜き出し」に譲りたいと思いますが、ジルベルトさんは名簿のひと言にも表れているように、いつも、新たなものの見かたを、それとなく示してくださるおかたでした。それは翻せば、おたがいの来しかたの違いであり、商家の三男坊と王族の末姫、という生まれの違いが意味するものであると感じています。そのひとが、どのように見て、感じ、考えるかで、大抵のことはおおむね知れる。いわゆる身分差の表しかたとして、こういう描きかたもあるんだ……という、まあ情けないくらい頭のわるい感想で恐れ入りますが、そんなふうにしみじみと、キュクロスの人びとにとっては何気ない日常のうちから世界観が匂い立つような筆致に、幾度となく心を揺さぶられ、ときには天を仰ぎ、ときには胸を押さえて床をのたうちまわり、すっかり虜となっていた期間中でした。ここが推しの最前列。
また、こちらはキャラメイク時点での想定として、物語の核心(騎士に「半分の姫」の処分命令が下された)あたりでは、かなうならお相手さまと剣を交えてみた~~いという下心が、あったの、ですが……。よもや序章から(こちらは手合わせとして)かなうとは夢にも思わず、めぐりあわせの妙に感激で指先が震えていたことも、いまとなっては懐かしい思い出です。モチーフのリフレイン、あるいは反転、たくさんたくさん肖らせていただいて、楽しませていただいた本編でしたが、ほんとうに最後の結びとなりますいま、少しでも、ジルベルトさんやPLさまからいただいた、うれしく、しあわせな気持ちをお返しできていたなら、これ以上のことはありません。まことに、まことに、お世話になりました。ありがとうございました。いつまでもずっと、大好きです!!!
◆イメージ500色の色えんぴつ TOKYO SEEDS
アメリア || SWEET EMBRACE | 甘い抱擁 | ささくれた気持ちをとろけさせる、甘やかなハグの色
アナスタシア || LUSCIOUS LAWN | ふかふかの芝生 | チクチクよりも心地よさが勝るふかふかの芝生色
アルシノエ || WATERLILY LAKE | 睡蓮咲く湖 | 湖面のキャンバスを清楚に彩る睡蓮の花びら色
レティーシャ || SWEET TEA | あまいお茶 | 甘いミルクティーの香りが誘うやさしい目覚め色
レイチェル || BOUNTY BLISS | 惜しみないしあわせ | すべてが愛しくなるようなシーツの中のぬくもり色
ロクサーヌ || BRIDESMAID'S GOWN | ブライズメイドのガウン | しあわせに。親友を祝福するブライズメイドの祈り色
サラヴィリーナ || CRISP AIR | すがすがしい空気 | 清らかな空気を朝ごはん代わりに胸いっぱいに、な色
アルバート || SPELLBOUND SPARKLE | おまじないのキラキラ | おまじないを唱える口元からこぼれるキラキラ色
バートラム || GLAZED CHERRY | シロップ漬けのチェリー | シロップにつけた甘いごほうびのチェリー色
シリル || RED LICORICE | 赤いリコリスキャンディ | 挑発的な赤いリコリスキャンディー色
エリック || GOLDEN HOUR | ゴールデンタイム | 明日のしあわせを祈る昼と夜の境界時間色
ジルベルト || TERRACOTTA TERRACE | 素焼きのテラス | 素足でたたずむテラコッタのテラス色
ケヴィン || NIGHT SWIM | 夜を泳ぐ人 | 星と雲にご用心! 夢心地の夜空の遊泳色
リューヌ || JACARANDA SNOW | ジャカランダの雪 | 舞い散るジャカランダの花弁の儚さ色
(双剣と盾)[序章]
なにか悪い冗談のように見えていたまっさらなサーコートの白が、青灰のもとに並ぶと、そのためにあつらえたかのごとく誇らしげに映る。)[序章]
うららかな陽に誘われ、気の小さな生きものが巣穴から顔をのぞかせるように、そろとまぶたが上がり、まなざしが交わる。男の胸に寄せる静かな波は、感情の読みとりにくい面構えではなく、まっすぐに正す背筋のほうに先ぶれとなって表れた。)……城に上がった年、夏のあいだ、彼のもとで学びました。彼の剣筋は、ほんとうに……ほんとうにうつくしい。迷いも、一点のくもりもなく……研ぎ澄まされた唯一のたましいが、あの切っ先には宿るのです。いつか私もこの手に、と……そう夢想もしますが、ああ、まだとても……。(薄い唇の端が不恰好に持ち上がり、笑みらしきものを形づくった。使い慣れない顔の筋を呼び覚ましたせいで、頰が細かに引き攣れる。普段なら、誰に明かすのもためらう胸のうち。同じ師の門人に出会えたうれしさが、男の口をなめらかにしていた。[序章]
ちらりと見えた手のひら。指の形。おそらくは、一年や二年でそうなったものではない。長い歳月を重ねて、少しずつ鎧われた皮膚。)……はい。すぐれた者ほど、その剣筋をもって、雄弁に語るものだ、と……。振るう一手で、相手の来しかたに触れ、おのれの信条をあらわす。そういった剣の道を追い求めるのは……、(たのしい、と。そう大っぴらに口にするのは憚られ、結びを曖昧にふやかした。騎士のありかたというものを、いまだ測りかねている。よい弟子、との言葉に、そうであれたらいい、と飾ることなく望む気持ちもたしかにあって、唇は慣れぬ形を繋ぎとめたまま。)[序章]
(ほかならぬ姫ぎみの唇がつむいだことに、少しも驚かなかったと言えば嘘になる。双ツ首の竜と騎士。謂れを知らぬ者は、きっといないだろう。王城のいたるところ、円柱の陰で、回廊の隅で、絶えずささやき交わされるのは、末姫が持つ奔放な気風についての噂ばかりではない。――半分の姫。騎士の英雄譚と起源を同じくして、明暗わかつさだめ。いにしえの地、竜の今際に吐かれた息の緒が、はるかな時をこえてなお、この国に絡みついている。[序章]
――視線は下りて、細剣に縫い留まる。口を開く代わりに、害心はない、と知らせるゆるやかな動作でおのれの剣帯に手をかけ、得物を鞘ごと外し、彼女の前に横たえた。魔物相手に構えるものとは違う、片手に振るうことのできる長剣。)……レイチェルさま。手合わせの機会を、私にくださいませんか。(褒められた話ではない。近侍を命じられたばかりの身で、ものをねだるなど。まして、刃を交えたがるとは。ともすれば、叛意と捉えられてもしかたのないふるまいでもあろう。暗く影がさす男の面にあって唯一、光を帯びる両の目が、落ちる髪の紗幕を透かし、揺らぐことなく一対の蒼穹を見つめる。)[序章]
……知って、ください。レイチェルさま。あなたの、騎士が……どんな剣を、どのようにして振るうのか。……俺も、あなたを知りたい。(紙やすりのようにざらついた、かたく冷たい指で、差し出された手のひらを包みこむ。おのれと比べて随分と小さい、と感じるが、その手ざわりは、やわらかに沈みこむ淑女の肌でもなければ、骨の太さを予感させる少年の肉づきでもない。たゆまぬ研鑽によって日ごと形づくられてきた、彼女の生のありかただ。)[序章]
長髪を高く結い上げて馬の尾のように垂らし、額にひとすじ、ふたすじ落ちかかる後れ毛の影に、ひっそりとしたまなざしをのぞかせた。踵を打ちつけて地面の硬さを確かめると、左足を軽く後ろへ引いて立つ。右手、下段に構える細身の刀身は、男の腕の付け根から指先までとほぼ同じ長さ。ふたりの間合いは大きく駆けて三歩ほどか。切っ先を斜めに下げ、まずは、彼女の一手を迎える姿勢にて待ち受けよう。かすかな頷きを開始の合図として、いざ尋常に――と、その直前。)――負けません。(相変わらず抑揚の薄い、けれど、気の昂りを抑えつけるような低い声。)[序章]
――レイチェルさま。あなたは、その剣で……(ほとんどささやくような、静かな声音で問う。)……双ツ首の、竜を討つのですか。(双頭の竜。安寧の世において、人びとにもたらされる謂れなき穢れ。彼女がただ、たのしい、という心だけで剣をとっているのなら、こんなに喜ばしいことはないだろう。分を弁えず、おのれが何ごとかを推しはかろうというのですらおこがましい。けれど、もし――彼女がその剣をもって打ち倒さんとするものがあるならば、知りたい。騎士として、共に剣を振るう者として、彼女の傍にあるために。[序章]
吹き下ろす風の一閃、迷わず大きく腕を払うと同時、地をえぐるような刺突がサーコートの裾をとらえ、ひるがえる布地を斬り裂き、そして――。)…………、(勝負のゆくえは見えていた。曲がりなりにも武人の端くれ、姫ぎみに仕える身として、そうでなければ立つ瀬がない。剣先を下ろし、しかし、と男は円柱の影に、幼い姫ぎみの姿を思い描く。生まれ持った身体のつくり。境涯の違い。騎士と姫ぎみを隔てるものがなければ、はたしてどうだったろう。[序章]
かつては剣を振るえなかったというこの闘技場で、呪いをそそぐ、と彼女は言った。その身をもってあかすのだと。憔悴の色が滲む相手に対して、男のほうは大きく息を乱しはしない。けれど胸の下には、肋骨を破らんばかりに打つ鼓動。これは高揚か、それとも畏れだろうか。剣を鞘へとおさめ、相手を見下ろして背を屈めた。清い汗が浮かぶこめかみに口もとを寄せてゆき、形のよい耳朶にささやき入れる。)勝ちを、ゆずったままには……なさいませんね。……いつか、また……あなたと、抜き身の刃をまじえたい。[序章]
――後日、騎士がまとうまっさらな衣には、ひとつのほころびが残されていた。男の手によってがたつく針の運びで縫い合わされた、かぎ裂きの跡。このサーコートは不器用な修繕を見咎められ、いく度も新調を勧められたが、持ち主が断固として拒んだために、過ぐる日の一幕を秘したまま、ふたつの季節を越えることになる。)[序章]
――王国はこがねの秋。小麦やとうもろこしの粉をひく水車の音。手足の先をぶどう色に染めた、果実酒づくりの娘たち。そうしたのどかな風景を離れ、日ごろはもう少し垢ぬけた顔でいる城下の町も、収穫祭の時季には土のにおいや家畜の鳴き声が押し寄せて、たいそう愉快な賑わいとなる。姫ぎみの傍らにひっそりと控える騎士とて、今日ばかりは誇り高き紋章を背負ってはいない。得物は小振りのものをひとつきり、商人ふうの丈が長い上衣に忍ばせていた。)……果実の種を飛ばして競う、催しや……闘鶏の賭けごとや……そういった遊びをなさるのであれば、町の娘さんふう、では……いささか、人目を引きます。[一章]
祭りの日には、やたらと腰の低い“主人”や、銅貨の扱いもろくに知らぬ“従者”が増えるものだ。[一章]
もちろん、おともしますが……ああいった踊りは……私は、あまり得意ではありません、から……。不始末があれば……この脚を、切り落とす覚悟で……。(手と手をとり合い、簡単な拍子を覚えてくるくる回るだけの遊戯が、男にはどういうわけか難敵なのだった。自分の脛に蹴つまずいてひっくり返るくらいならよいが、万が一にも姫ぎみの足を踏みつけるわけにはいかない。女官長の諫言などどこ吹く風、日ごろ姫ぎみと得物を打ち合わせ、いつぞやは――ただ一度きりのことであったが――その眼前に真剣を向けさえしたくせに、深く思い悩む様子で片腿に手のひらをあてる。やわらかなほほ笑みに頷きを返す男の顔は真面目そのもので、冗談のつもりではないようだった。)[一章]
……では……ねえさま?[一章]
……はい。本日は……“ジル”が、おともをいたします、ねえさま。[一章]
城下はたいへんな賑わいだった。早くも酔っぱらったような足つきの楽師が、調子はずれにつまびくリュートの音。ここぞとばかりに飛びかう客寄せの声。焼き菓子の甘い香が鼻をくすぐり、肉や魚を揚げる匂いが腹をつつく。冗談のような大きさの野菜や、毛づやのよい仔牛を乗せて通りすぎるのは、品評会に向かう荷車だろう。行きかう人びとに紛れて、例年通り、お忍びで市井の祭りを楽しむ貴族の姿もちらほらとあるようだ。[一章]
――その紳士は、ダニエリの家とも付き合いのある宝石商だった。騎士が随伴した先の夜会では、礼節も忘れ、子息を売り込むことに随分と熱心なようだった、と記憶している。しまいにはおのれが間に入り、姫さまはご気分がすぐれない、とどうにかお引き取り願ったのだが。品定めでもするかのような目つきが、姫ぎみへと向けられるのを見て――皮膚の薄い眉間にはっきりと、地割れのごとき皺を刻む。[一章]
(ねえさま。末の姫と血を分けた王女たち。そのひととなりをよく知らぬ男は、往時を偲ぶ語らいのなかに、時おりその面影を想像するのみだ。姫ぎみや、彼女に近しい側仕えの者たちから伝え聞く“きょうだい”の姿は、血のかよったあたたかな実像を伴って、彼女の傍らにあるように思える。それはなにより頼もしく、うれしいものと感じられた。王城の内と外、姫ぎみに向かって放たれる、毒矢じみた視線はただでさえ尽きない。盾のひとつでは到底足りぬほどに。[一章]
彼女の胸のうちにかかる霧を晴らしたい一心で、けれど糸口を掴めないまま、手にした花の一輪を見る。初めに目を留めていた、小さな花弁。みずみずしい白は、鮮度を保つための術を施されていない、生きたままの色あいだろう。飾って半日も歩けば褪せてしまう、今このときだけの儚いうつくしさ。)……ねえさま。(低く呼び、こちらへ注意を向けさせたなら、伸ばす手はボンネットの庇をくぐり、耳もとへ。節くれた指で後れ毛をさぐり、絹の髪に青い茎を分け入らせる。)……いつでも、俺が……あなたのお力になります、から……。[一章]
(受け取る愛らしい花弁は、ふと目を留めた者の胸にほのかな光を灯してくれる、可憐な風情だった。花を贈られるなどそうないことで、指にそっとつまんだまま、しばらく大事そうに眺めて歩く。通りの向こうから近づく音楽にうながされてやっと、胸もとの飾り紐に細い茎をさしこみ、決してなくさぬよう固く釦をとめて。)……はい。うまくやれると、思います。あなたが……隣に、いてくだされば。必ず……。(剣を握り、人の手を取る。ふたつの間にある隔たりのことを考えた。だが――あの春の、すばらしい秘密を分かちあうこのひととなら。約束の踊りの輪が、若いふたりを陽気に手招く。[一章]
奏でられるのは、夜会に聞くようなかしこまった旋律ではない。麦穂を打ちながら、牛を追いながら、親から子へと歌い継がれてきた、のどかな調べ。実りある大地に感謝を捧げ、産み落とされた命をいつくしむ。よろこびの歌が空へ響きわたるとき、そこに蔑みの目はなく、責め立てる声もない。老いも若きもひとしなみに輪になって手を叩き、踵を鳴らし、肘をぶつけて笑いあう。時おり誰かが足の運びを踏み違えると、なだれるように旋回の向きが変わり、もつれあった娘たちが楽しげな悲鳴をあげた。体勢を崩しかかるたび、男の乾いた手のひらは大げさなほどの緊張感をもって、隣にある指をしかと握りしめたが、そのぬくもりを拠りどころとして、どうにか口を開く余裕も生まれ始めている。奇跡的に、まだ誰の足も蹴飛ばさずに済んでいた。)[一章]
ささやき落とす声は、容易ならざる重大な秘密を明かすように。)……たのしい、です。(男にとっては、唇を湿らせる程度のささやかな一杯。この程度で酔いがまわるはずもない。けれど、甘い酒精に巻かれてつい口をすべらせたのだ、というふうに、夢と現の境にいるひとのような、ひとりごとめいた言いかたをした。)あなたといると、俺はたのしい……。(――やがて祝祭の日は暮れて、連れ帰った可憐な花弁を窓辺にそっと横たえ、月あかりのもとに眺めるとき。男の耳に遠い鐘の音がいつまでも響きわたり、低く掠れる声は、祝いの歌をいく度もなぞった。幸いあれ、いとし子よ。老いも若きも、生まれや立場さえも飛び越えて、ひとしく祝福されし命よ。そのゆくてに幸いあれ、幸いあれ――。)[一章]
(宣誓)[二章]
両手に構えるひと振りを空にかざし、視界を曇らせる霧ごと鳥影を薙ぎ払う。鈍く光る切っ先で、ねじり貫く。切り裂き破る。枷をはめられた囚人のような、倦み疲れた手脚を重く引きずって、叩き割る。蹴り砕く。磨り潰す。力にまかせ、相手を確実に屠るための剣を打ち振るい、害なす一撃を馬車まで届かせはしない。時おり屋根にぶつかって音を立てるのは、とうに事切れて刎ね飛ばされる頭や翼の残骸だ。――やがて、ちょうど一曲を踊り終えるくらいの時を経て、耳にこびりつく禍々しい叫びが絶える。[二章]
片方の瞳をゆっくりと瞬かせ、次に口を開くまで、束の間ためらった。)……ジルは、大丈夫です。レイチェルさま。大丈夫ですから……。(親が我が子の耳もとで、よく眠りなさい、とささやき、すべての不安を取り除いてやりたいと願うときの、やわらかな声の形。愛し子の髪を撫でて毛布にくるむ代わり、まなざしを交わらせて、唇をほとんど動かさずに、葉擦れに紛れるほどの小さな音を残した。[二章]
少し思案げに視線を揺らしてから、)――そう、ですね。我々は、もうよい大人ですので……このなりでは……。(窓の向こうのほほ笑みに、意味ありげな目配せをしてみせた。手合わせの場に選んだ中庭が、前日の雨によって恐ろしくぬかるんでいたときの話だ。泥だらけのまま、構わず棒きれを打ち合わせる姿を女官長に見咎められ、子どもじゃないのだから、と小言より先に呆れられて、ふたりで顔を見合わせた。あの日ひときわ悪戯っぽく、おかしげに輝いていた瞳を思い出し、符牒めいたやりとりで、少しでも彼女の気分が上向けばと考えたのだったが――姫ぎみがどう記憶に留めておられるのかまでは、男にはわからぬこと。[二章]
こわい毛の、長さがあるものは絨毯に……細く、やわらかいもの……これは、薄い織物に適しています。……同じように、群れには……生い育つに向かぬ個として、生まれつくものがあるのです。(誰がそう定めたのでもない元来のかたちを、人の手によって選り分ける。質のよい血統を残すため、古くから受け継がれてきた営み。間引かれる羊は肉や革に姿を変え、人びとの蓄えとなるのに“適して”いるのだ、と――そうともとれる言いかたをして、静かなまなざしで彼女を見下ろした。)[二章]
……さまざまな個を抱える、そのありかたは……おっしゃるとおり、似ている、とも申せますが……。……ひとと、羊は違います。(体温の低い手は撫ぜ下ろすように肌へ触れて、きつく固められた拳を開かせようとした。手のひらがなおも閉じたがるのであれば、おのれの無骨な指を握りこませて。)あの羊は……人びとをあたため、滋養を与え……冬を耐え忍ぶための、糧となる。選り分けた命が生み出す、よりよい質の羊毛は……暮らしを豊かにし、飢えや病から遠ざける。(宥めるでも、諭すでもない、淡々とした語り口。絶大なる力によってふるいにかけられれば、ひととて羊のように死ぬ。それが天命として、身をゆだねることもできようが――時に剣を、時に盾を持ち、生き抜くすべを、執拗なまでに強固な糸で編みあげるのはなにゆえか。)[二章]
……そうして、“めぐらせて”ゆけるのが、ひとなのだと……俺は、思います。生きようと伸ばされる手を……誰ひとり、離さぬために……。[二章]
続けて「できます」と頷く所作には、ためらいも、わずかの迷いもなく、重ねる手を彼女の目の高さまですくいあげて。)あなたは、この御手で……それを成せるかたです。(固く張りつめた皮膚。なぞると凹凸を感じる指の節。いく年もかけて築きあげられた、うつくしい矜持。そのかたち越しに彼女を透かし見て、笑む。男の、顔の筋をぎこちなく歪ませる下手な微笑のやりかたは、いつしか凍った土を溶かすように、自然な形でまなじりや唇へとなじみ始めていた。[二章]
――姫ぎみと共に部屋を辞した男は、付き従う後ろからその背を注意深く見守った。回廊をゆく、心ここにあらずといったふうの足どりが、それでもこの場所へたどり着いたのは、思うところがあったのか、知らず知らず導かれたものか。まぶたを重く持ち上げて、なかば髪に隠れた目に石造りの柱を映す。)――……はい、姫さま。陛下は、たしかにそうおっしゃいました。(落陽が一面に溶け出したかと思うほどの空だった。円柱の影が石敷きの床を舐めるように長く伸び、男の姿はそのなかに沈んでいる。背を向けて立つひとの問いかけに、まずはのべねばならないことがあると――そう思いながらも、なにかが舌を張りつかせ、言葉を喉もとに押し留めた。)[三章]
姫さま。……もうじき、日が暮れます。こうも、人の目の届かぬところにいらしては……。風も、随分と冷たくなりました。お戻りに、なりませんと……。(顔を俯けたまま、婚前の淑女が日に百ぺんも聞かされるような、もっともらしい抑揚を含めたつまらぬ進言をする。昨日までの男であれば、こういった、頭ごなしに諫める物言いはせずにいた。動揺の見える彼女を落ちつかせようと、その背にそっと触れさえしたはずの手も今は拳に握られて、ただ膝上にある。かつて闘技場に響いた、高らかな剣戟の音などまるで知り得ぬかのごとく。足もとに広がるサーコートの裾、そこに留められた不恰好な縫い跡だけに、過日の片影が残されていた。)[三章]
その姿は、忘れ去られた庭に佇む石像のように、うら寂しい闘技場の黄昏に溶けこんだ。問いかけに返す答えの代わり、地をすべった視線が、影になって細く伸びる蔦の葉の輪郭を捉える。)……では、……離さずに、いてくださいますか。(ため息ひとつにかき消されるほどのささやきだった。暗がりに目が慣れたなら、濃く落ちる影のなかに浮かびあがるものがある。見る者を鋭く貫かんとするまなざし。男は眼窩に暗い熱をくすぶらせ、彼女をまっすぐに見つめていた。)[三章]
……ジル、と……あなたに、そう呼ばれるのが好きでした。このまま、ずっと……おそばに、お仕えしたかった。(乾いた唇を割る声はほとんどうわごとじみて、追いすがるようでも、慈悲を乞うようでもあった。彼女の手は、民びとが生涯抱えるより多くのものを与えられ、同時にうしない、そしてまた受け入れねばならない。みずからの貴き身をもって、国の礎となるために、花弁のひとひら、糸の一本、よすがにすらゆるされず。子どもの駄々にも満たないと知ってなお、明かす思いを恥じてまぶたを閉ざす。引き絞った弓の緊張を見せていた肩の線が、それを境にふっとゆるんだ。)[三章]
……ありがとうございます、姫さま……。私は……だめにして、しまいました。ハンカチも……申しわけありません……。(触れ合わぬほうの手で、衣の胸もとより、畳まれた手巾を取り出しておのれの片膝に乗せた。叱られると思ったわけではないが――ずっと言い出せずに、“借りた”という名目のもと、肌身離さず持ち歩いていたそれ。汚れを落とそうとして、魔法を使わぬ古くからのやりかたで苦心した結果、繊細なレースはすっかり形が崩れている。その一端をつまんで広げると、干からびきって元の色さえわからなくなった花弁がはらはらと剥がれ落ちた。いずれも他人の手を借りれば済んだものを、すべて台なしにしてしまった。子どもじみた独占欲を抱いてよいおかたではないと、初めから承知していたのに。)[三章]
(おのれが捧げられるのは、この身ひとつ、心ひとつ。それでもいつの日か、兄たちと同じく妻を娶り、かわいい子をなして。抒情詩にうたわれるような、うつくしい一頁としてこの日々を振り返る――そういった未来を、束の間、思い描いた。隠修士にでもなって、遁世の果て、どこか遠い地でひとり骨を埋めるほうが、よほどましであると言える。近く重ね合わせたがるまなざし、男の両目に宿る熾火の熱は隠しようがない。しかし彼女が、この別離を穏やかなものとして迎えようと心を砕いているのがわかったから、薄い唇はほほ笑みの形にひらいた。)[三章]
――微笑の薄れた唇が、なぜ、と音なく動く。いつものように、悪戯っぽいからかいを滲ませた末姫の顔の奥から、“それ”が現れるのを見てしまったために。なにも持たぬ少女のような、無防備な羨望がこのひとにもあるのだと、あたりまえのことを考えるよりも先に――)姫さま、(地を這う影が人知れず領土を増やすように、おもむろに身を乗り出す。大きく広げた五指を彼女のおもてへ迫らせ、清らな瞳の上へかざして視界を覆い隠した。ぐっと手のひらを押しつけると、指の背に頼りなく引っかかっていた花弁、色褪せた最後のひとかけらが、白くやわらかな頰へすべり落ちてゆく。)――逃げて、しまいましょうか。(ひとところに絡みついて姿を変えぬ蔦の、乾いた葉擦れの音も今はない。)[三章]
(堪えるように握られていた拳は、いつしか彼女の指先を離れて、その背を強く抱く。焼けただれた喉奥から、無理やりに押し出すような声でつづる夢語り。よこしまな意志を持つ者が、まっとうな身なりをして耳もとでささやき、気高い精神をそそのかし、堕落させようとするときの愚かな響きだ、という自覚があった。それが苦しげに聞こえるのは、甘言にたぶらかされる心ではないと知るゆえに、必ず踏みとどまるひとと知るゆえに、最後はその小さな、彼女自身の手で確実に断たせねばならない思いだとわかっているからだった。)……ねえ、レイチェルさま。今すぐに、逃げ出してしまいましょう。[三章]
……あなた自身で……そそがねば、ならないのですね。遠く、遠く……たとえ、誰の手も、目も届かぬところへ逃れようと……あなたが、心に勝利のあかしを打ち立てる日まで……その呪いは……。(独白めいた声色が、“呪い”と、そう口にするときにだけ、わずかばかりの翳りを帯びた。ゆっくりと、なにかを強く抑えつけるような瞬きののち、埋み火の熱をまとっていた瞳の色は、いつしか穏やかな湖面のそれへと変わりゆく。)……よいですか、姫さま。ジル、と……その呼び名は、もう二度と、口にしてはいけません。……けれど、……もしも、手が……この手が、あなたの支えとなれる、そのときは……、(正しい従者の顔をして、秘めごとを潜ませた。肌守りの石をそっと握らせるように。)どうか、約束してください、レイチェルさま。ジルをきっと……あなたのもとに、呼んでくださると……。[三章]
(細く震える肩。あふれ出す嗚咽。胸を締めつけるような息づかい。心のままに明け渡されるかなしみ。そのすべてをただ静かに受け取っていた男は、年端も行かぬ子を抱くようにして、腕のなかの面差しをしっかりと覗きこむ。)いいえ、姫さま。私は……あなたを、誇りに思います。(倒れ伏して涙に暮れるより、立ち上がって剣をとる道を選んだひと。泣き腫らしたまぶたに、冷たい指で触れる。斜陽は銅の輝きを過ぎて、辺りは薄暮のなかに沈みかけていたが、男の網膜にしがみつく光の残像が彼女のもとへまといつき、潤む瞳のなかを漂ったので、その澄みきった色は一層きらめいて見えた。[三章]
(優秀な兄たちは、今やダニエリの中枢に座している。絵に描いたような家族愛、というわけではないが、心から厭うて遠ざけ合う仲でもない。ただ、たまの食卓を囲むとき、話題を探して気まずく目を逸らし合うような。幼いころからそういう関係を保って、ここまで来てしまった。均衡を崩さずにいるのは、互いの性分ゆえである。付きびとの任を終えたら、と思う。久々に顔を見に行こうか。今ならきっと、腹を割って話せるだろう。いつか言えなかったことも。[三章]
王后さまの、お支えはもちろん……姫さまがこうして、すこやかにお育ちになられたことが……どんなにか、陛下のお心を慰めただろう、と思います。(玉座の孤独とは、おのれには到底はかり知れぬ、厳しく、険しいものであるのだろう。国王とは、王族とは、時に親や子の結びつきすらも離れて、孤高にあらねば立ちゆかぬのだ。だから――先の場があたたかな祝福にあふれていたことが、改めて男の心を安らがせた。形あるものを持ち出すことがゆるされずとも、編まれた願いはまとってゆける。生涯、彼女を凍えさせぬ衣になる。えにしもまた、と頷いて、)……、私、が……、(息を呑んだ。その言葉が、胸に歓喜を生み、熱い血を四肢にめぐらせる。瞳は大きく揺らぎ、酸素を求めるように開く唇は、けれど言葉を持たない。ただ手巾を胸に抱いて、深くこうべを垂れた。)[三章]
――明けの兆しにはまだ遠い。尖塔を後に、しんと冷える夜をゆく。やがてひとけのない歩廊へ出ると、荒い靴音はそこで唐突に止まった。おもむろに振りかざす拳が、重く倦んだ剣筋に似て石柱へと叩きつけられる。鈍い音が跳ね返り、皮膚が裂けて血が滴ったが、色が失せて蝋のようになった面は固く凍りつき、微塵も動かなかった。ほんの些細な震えでひび割れ、たちまち砕け散ってしまうと信じているかのごとく、乾いた唇は呼吸さえも恐れているようだった。)[四章]
――王城の奥、封じられたひとかどに蔽われ続けた最大の禁秘。明かされてしまえば、記憶を照らし合わせるまでもない。呪いがどうやって産声をあげ、ひとの目を閉ざすのか、男は知っている。だというのに、よもや王室が、忌み子を揃って生かすはずがないと思い込んでいた。いや、思い込もうとした、のか。そそぐべき呪いがあるならば、まさにそうした愚かしさこそを指す。過ぎにし十と七年の追憶に、遠くまなざしを向けながら、一国の王であり、双ツ子の父であるひとは語った。今こそ罪をあがなうとき、と。――胸もとへ収めた手巾に、衣の上から触れる。気の慰めというより、もっとたしかなよすががそこにはあった。たとえばそれは、すべての命がひっそりと息絶える夜、高き峰にかかる雪の向こうから現れる光のかたちをしている。生きておられたのだ。我が国における災い、存在のゆるされぬ双ツ子が、どちらも害されることなく、この日まで。もはや、その事実だけで充分だった。[四章]
(春へ)[終章]
……これを……姫さまに、お返しいたします。(定めの夜から数えて、十といく日か。“表”に現れるひとりの姫ぎみに、騎士はこれまで通り、影のように付き従っていた。ずっと忘れていたものをたった今思い出した、というふうに、そっと彼女の手へそれを握らせてみせたのも、なんら変わらぬ付きびとの顔をして、一日の務めを終える間際のこと。上等な作りに似つかわしくない、形のよれて崩れたレース飾り。この世にふたつとない真白い手巾は、そうして正しい持ち主のもとへとわたるだろう。そのかたく張りつめた、うつくしい指先が布地を広げるとき。そこに忍ばせた蔦の葉が一枚、符牒めいて舞い落ちる。[終章]
円柱にかける指は、手慰みに蔦の葉へ触れ、その形をなぞる。乾いたつるが蛇のように這い下りる根もとに、古びたランタンをひとつ置いていた。楕円に広がる灯影のもと、近くに寄れば、互いの表情が難なく見て取れるほどにはなるはずだ。しかし騎士は蜜色の光に背を向けて、振り返らぬまま足音を聞く。顔をそちらへ向けずとも、誰のものかわかる。そのくらいの月日を共に過ごした。)――王命を、授かってまいりました。(情の一切を荒く削ぎ落とした声だった。その切り口一面に鋭い棘が立ち、触れようとした者を殊更に遠ざけんとするかのような、耳にざらつく響き。)姫さま。あなたには、お選びいただかねばなりません。[終章]
(うら寂しい闘技場にふたつの影が揃うと、紗幕を引くようなささやかさで障壁が閉じる。防音と人払いのためのまじない。高位の、たとえば王室が抱える術師の手によるような、精巧に編まれた術であると――彼女であれば判じられるだろうか。いずれにせよ、警告じみて明確に差し込まれる、他者の気配があった。鋭いまなざしに似たその違和を、騎士も感じ取って素早く視線をめぐらせたが――今は取るに足らぬものとして捨て置き、背を向けたまま語り始める。[終章]
今が“その時”であると、陛下は仰せです。末姫の片方を処分せよ――王立騎士団所属、ジルベルト・ダニエリが、こたび、拝命つかまつりました。貴き御首を、卑しい刃になぞ晒せぬというのであれば――今、ここで自害なさいませ。[終章]
一拍おいて石敷きの床に踵が鳴ると、結った髪が揺れて広がり、肩をすべった。遅れて振り向く双眸はなにものにも覆い隠されず、ランタンの火に明るく浮かびあがる。相手の心をただしく映しとろうとする、穏やかな湖面の静けさ。)……あなたの、呪いは……、(対峙する影に佩刀の形を認めてなお、騎士はおのれの柄に手をかけようとしない。今、翔ける鳥の速さで飛び込んでこられたなら、たやすく心の臓を明け渡してしまえる。そういった姿で、力を抜いて開いた両の手のひらを下ろし、ただ佇んでいる。)……あなた自身で、そそがねばならないのだと……私は、申しあげました。あなたのお心に、生み出されたものならば……たとえ、どこへ逃れようとも、あなたの手で、たしかに“打ち勝った”と……あかしを立てるまで、生涯消えぬもの、と……そう、考えたからです。[終章]
(やはり、という思いがあった。彼女はなにひとつ、知らされていなかった。心身を一瞬で支配する、我を忘れるほどの怒りというものは、あの長い夜から時間をかけて噛み砕かれている。今はただ、暗く底の見えない水面を覗きこむような、空虚な哀しみばかりがこの身のうちにある。十七年もの歳月を、覆い隠され続けた“唯一”の真実。[終章]
(――わからない、と、そう返る答えに、騎士の口の端には少し、ほんのわずかに安堵がよぎった。生まれながらの罪。災い。呪い。そんなものの何たるかなど、この世の誰にも知り得ぬことだ。知らぬからこそ、その透明な脅威がいつか我が身に及ぶことを、みなが恐れる。[終章]
いつかの問答をなぞる声が、輝く春の記憶を呼び起こした。“あなたは、その剣で――”)――……いいえ、姫さま。呪いを、そそぐのです。(静かに長剣を抜き放つ。肩を引き、中段に構えた右の手に、もう一方の指を添えた。水平に向ける切っ先が、揺れる灯影を弾いて光をまとう。踵がかすかに上がり、そのまま踏み込むかと思われた足はそこへしばし留まって、)[終章]
産声ひとつ、懇願ひとつあげることすらゆるされなかった、幾多の命が眠る大地。滔々と継がれてきた円環の――その果ては、しかし。)――今は亡き、母ぎみが……あなたがたふたりを、みごもられたとき……、(国中が、たいへんな騒ぎになったという。男はまだほんの幼子であったから、当時の世情を知らない。どこか懐かしむような、やさしげな響きで紡ぎ出すのは、いつか、そうやって語ってくれたひとの声を、追憶のなかに辿るからだった。)間違いなどないはずの、貴き血に現れた、そのしるしが……卑しき我らのもとに、降りたとて。一体、なんの咎があろうと……生きることをゆるされた、双ツ子たちが……わずかばかり、いたそうです。(やがて、末姫は“半分”で生まれ落ちたと、そう公にされるまで。そしてそれからも。円環に生まれたひずみに、肩を、背をあたたかく撫ぜられ、励まされて、夜の底をからくも生き延びた人びと。彼らの目を借りて彼女を見つめるように、瞳はそっと細まる。)[終章]
そうして、たしかに産声をあげた、小さな命が……あたたかな腕に抱かれて聞く、祝福は……それは、呪い、だったでしょうか? すこやかに育て、と生かされた……その子らが、背に負うものは……それとも、願い、だったでしょうか、姫さま。(――呪いだ、と、あるひとは言うだろう。いかに世間の目をごまかそうと、忌み子の行き着く先は知れている。焼けた石の上を裸足で歩ませようとする、それは呪いにほかならないと。願いだ、と、またあるひとは言うだろう。捨て置けばやがて潰える命を、束の間でもいい、今このときだけでも。生きなさい、とすくい上げる手。それこそが願いだと。因果が幾重にも絡んで育ち続ける円環に、まことの形などありはしない。まして、この剣で正すべきひずみなど。[終章]
……はい、姫さま。……わからない、ということは……選び取れると、いうことです。[終章]
――きん、と澄んだ音が空に砕けた。白じろとした刃が光る牙に似て迫り、あわや柔肌を切り裂くかと思われたその瞬間、手首を鋭く返し切っ先を逆に跳ね上げて、折れた剣身を高く弾き飛ばす。)……、……ジルは……ここにおります。あなたの……おそばに、おりますよ。(押し殺すささやきに、吐息が熱く滲んだ。聞いている、とうながす形で、剣先を下げ、ぬくもりを胸に受け止める。霞のように淡く広がり、溶けきった影に境界はない。ランタンが投げかける蜜色の輪をいつしか離れて、今はふたりともぼんやりとした月明かりの下、薄闇のなかにいる。乱れる鼓動も、息づかいさえも、やがてひとつに混ざり合おうという近しさだ。わずかに残された隙間すら埋めたがって、おぼろげな輪郭を抱きすくめようとする片腕には、少しのあいだ、その細い身体が浮き上がるほどの力がこめられた。)[終章]
幼子をかかえる手つきで、ふたたび頭を胸もとへ抱き寄せる。それから空気の流れを探るように鼻先を上げ、)――……王よ、(男が虚空に呼びかけると、すべての生きものが死に絶えたかのような静寂をこえて、遠く、泣き荒ぶ風の音が聞こえた。障壁が解かれたのだ。男の声に応じたのではなく、それはやはり警告であるらしかった。たとえば不用意なひと言で、たちまち何十もの兵がなだれ込み、冒涜者の喉を貫く用意がある、と示唆するための。肌を刺す気配は変わらずそこにあり、天に浮かぶ巨大な眼球じみて、ふたりを監視していた。)……円環の外へ……このひとと、共にゆきます。私は……キュクロスの騎士では、いられません。……ひずみなき真円にこそ、大地の摂理があらわれるのだ、と示したくば……もう、その目で見たでしょう。古き英雄の血を引く、みずからの手で……信条を、明かすべきです。(諦念の滲まない、乾いた声で告げる。[終章]
神話はもしもを語らず、しかし今を生きる人びとは、暗闇に一条の光を見いだせる。まなざしを胸もとへ戻して、)……あなたと共にあれるなら、俺は……。(ひと呼吸で言い終える短い言葉には、様々な意味が含まれた。なんだってできる、と応える頷きの仕草。これから進もうとする道に、迷いや恐れはない、と知らせるほほ笑み。)[終章]
(揺らぐ炎の影に、後ろ姿の輪郭が明るく浮かびあがる。目の奥に永遠に焼きつくかのように思えたそれも、すべてが終われば一瞬のこと。彼女が振り向く先で――男はまさしく、心底驚いた、という顔をしていた。とはいえ、この男をよく知る者が見るのでなければ、傍目には少し余計にまぶたと唇が開いたくらいの。ひとつふたつ瞬き、剣を握ったまま傍らに膝をつく。まず、片手にすくい上げる指先に火傷の痕がないことを確認して、軽く息を吐いた。それから、)……夜の、底へ……、(短くなった髪の、断たれたばかりの真新しい切り口へと触れる。女人の命と呼ばれる、その艶やかな絹糸を静かに撫ぜて。)……理の、外へ……地の、果てへ。……どこまでも、おともいたします。たとえ、すべてをなくしても……あなたの手を、離しはしません。このさき、ずっと……決して、ひとりにはしません、から……。[終章]
ランタンの火が大きく揺れて、星々の最後のようにひときわまばゆい輝きを放ち、ふっとかき消えた。それを機に立ち上がり、拾い上げた外套を彼女の肩へ被せてから、手のひらを差し出そう。彼女がいつもそうしてくれたように。――闘技場を背にしても、まだ首は繋がっているようだった。進む回廊の先、抑え込まれた息づかいに似て張りつめる空気を感じたが、突如として現れる障壁や、幾多の刃にゆく手を塞がれる兆しはない。城内から、不自然なほどにひとけが失せている。遠巻きに息を潜める気配をたしかに気取らせておきながら、許容ではなく、明確な排斥の意図をもって視線を逸らしてみせるような。円環の外で、夜の底で、存在し得ぬ亡霊がこの国に生きるとは、そうした見えざる目に晒され続けることであるのだろう。床下から冷たく染み出す夜気に、ふたりぶんの足音だけが響く。手を引いて先導する男は急く様子を見せず、あるじの凱旋につき添う従者さながら、その歩みは堂々としてさえいた。[終章]
(“ひとり”にさせてしまう、という思いがあった。片時も離れず固く握り合わされてきた、ふたつの手を無理やりに引き裂いて。もしも、この一夜がすべてを塗り替えることになるならば――と、手巾を託したそのときにも。だから――かすかに息を呑んだのは、驚きからではなかった。しっかりしろ、と背を叩かれたような心地で、宙から現れたそれを見る。)……、無茶を……なさっておいででなければ、よいのですが……。(揺れる火影に照らし出されて、男の双眸もまた親愛の情に満ち、灯火のあたたかさを帯びた。[終章]
――……シェリル。(“最愛”の意味を持つ、その響き。ゆいいつの名を舌にのせて、シェリル、ともう一度口のなかに転がし、まなじりを細めた。[終章]
外套と荷袋を受け取って胸に抱き、頭を俯けて、手巾に唇を寄せる。)あなたの名を……もう、ほかの誰にも、呼ばせたくはないと……少し……少しだけ。考えて、しまいました。これは……罪深い、ことでしょうか……。(自制と、なにものかの狭間に迷うような声。けれどひっそりとささやく口の端に落ちる影は、ほほ笑みの形にたゆたった。[終章]
――夜のしじまを連れ立って、やがてたどり着いたその場所も、ある意味では王城の“奥”だった。ただし、貴きかたがたの目にはまず触れないだろう一角である。この古い門扉をくぐるのは、主に死びとや罪人、不浄とされる荷のあれこれだが――後から与えられた役割の一切を取り払ってしまえば、ただのもの言わぬ鉄門。錆びついた落とし格子はなにを語るでも、糾弾するでもなく、ただ風に吹かれて軋んでいる。[終章]
では、まず……よい鍛冶屋を、見つけましょう。それから……医伯や、治癒者、薬師に……広く、門戸をひらく街を。医学の道もまた、多岐にわたるもの、と……そう聞きます。人びとに……手をのべるすべを……あなたが思い描く、未来を……たしかに、探せるように。(つらい試練を耐えたばかりで、目を先へ向けさせようとするのは酷なことか、と思う。けれど彼女の瞳は道に惑わず、凛々しく未来を見つめていた。それがなによりうれしく、誇らしい。もしも凍える風が忍び入り、痛みを呼び覚まそうと吹き荒れる夜があれば、この身は隣で寄り添う盾となれる。[終章]
――……考えて、おりました。正直に、申しあげるべきか……。(鞍に跨り、彼女の頭をおのれの胸もとに寄りかからせたのち。ややあってから切り出すのは、先刻、からかいと恥じらいの色を交えて投げかけられた問いへの答え。季節を越えて与えられた、ふたたびの――ゆるしについて。不揃いに切られた髪へ指をさし入れて、そのひと房を吐息で湿らせる。)……この御髪が、整うまでの……ほんの、ひとときでよいのです。……俺は……あなたが欲しい。あなたの、すべてが……。(華奢な体躯に両腕を回し、逃さぬよう抱えこんだなら、ひんやりとした頰を触れ合わせて。)俺に、俺だけに……シェリル。……ゆるして、くださいますか?(ささやきを溶かし崩してねだる。シェリル。きっとたくさんの声に、親しみと、愛情をこめて呼ばれるようになる名だ。はじまりに呼んで、誰よりも近くで呼んで。このうえない栄誉を授けられ、それでもまだ足りぬ、とさらけ出す胸のうち。調子にのって、とお叱りを受けるのであれば神妙に姿勢を正しもするが、外気から遮るように囲った腕をゆるめる様子はない。呼気に笑みの気配をのせて、先ほどは愛らしく染まっていたまなじりの色を、今は確かめられないのが惜しい――と、そういうことを考えている。[終章]
一度振り返って眺めた王城は、半円の月を背に黙してそびえるばかり。長きにわたって積み重ねられた威容に比べ、風に吹かれてこぼれ落ちる葉のように離れゆく影は、あまりに小さく見えるだろう。高き峰々のふもとにうずもれ、いずれ歴史のうろに葬られるはずだったふたつの名、そのゆくえが正しく語られることはない。けれど、のべられる手のぬくもりを、めぐり来る春のよろこびを、あたりまえに誰もが知る、そんな日が――いつか、この国には必ず訪れる。外套の合わせを広げ、共にあるそのひとをくるむように懐へと抱いて、男はまた前を見据えた。道をひらく蹄の音が、夜のしじまを裂いてゆく。生ける命の熱を連れて。今もどこかで産声をあげる、かすかな息吹を探して。)[終章]
(シェリル)[エピローグ]
――――、(ひとつの名を呼んで、腕のなかへ招く。質素な、けれど宿の夫人の手によって清潔に整えられた一室だ。年代物の寝台はふたりで腰かけるとひどく軋んだが、この世の終わりのようなその音にもじきに慣れよう。馬の背に乗るときのように、おのれの脚のあいだに座らせて、不揃いの髪を撫でた。つましい道中、手持ちの貯えと剣を振るって稼ぐ日銭があれば、当面の路銀を賄える。姉姫の心遣いをうれしく思いながらも、数少ない故郷の品を手放すには及ばないと、贈られた細工物の使い道は傍らにあるひとへ委ねていた。[エピローグ]
この夜、男が手にしたのは、そうした餞別のひとつであったかもしれない。無骨な指に握られた小さな櫛が、燭台の灯をこがね色に弾く。見下ろすつむじから、後ろ頭の丸みを通ってうなじまで、やわらかな髪をすくい上げてやさしく梳ると、あたたかな光の輪が広がった。短く断ち切られ、結うにも足らぬ絹糸が、ふたたび豊かに背へ流れ、うららかな陽を浴びて輝くころ。長き旅路の先に、新たな道がひらけているといい。花の一輪を贈る代わり、最後に指の腹でこめかみの産毛をくすぐって、もう一度呼ぶ。ゆいいつの。そして最愛の。そっとささやくたび、こうして触れあうたび、この身は焦がれている。やがて狂おしく育ちきる情が、胸のうちに息を潜めているのがわかる。――けれど、今はまだ。腕を回し、ぬくもりを抱きしめて、祝福の仕草で髪の根もとへ口づけた。)[エピローグ]
その手をとって、握ってね、わたし、きっとこう言うわ。
「大丈夫よ」と。「ともに、生きてゆきましょう」と。