Letitia Erda Kyklos
レティーシャ・エルダ・キュクロス
レティーシャ・エルダ・キュクロス
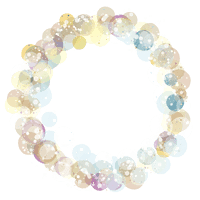
- 年齢
- 17歳
- 身長
- 160cm
- イメージカラー
- Foggy Rose
- 騎士
- シリル
ふたりでひとつとなるように。別たれることがないように。喜怒哀楽をばらばらにして、得手不得手は補いあって、痛みを刻むのはおなじだけ――幼い日から始まったごっこ遊びは今日までつづいている。そうしてそれは、性質としてすっかり定着していた。怒りと哀しみを担う娘から、喜びと楽しみを与えられた娘はたおやかな乙女である。世相など与り知らぬと無垢な微笑みを浮かべ、紡ぐ言葉はいとけなくも平穏そのもの。末の姫君は機嫌が好さそうな時こそ話が通じないと噂されるなかを愛犬を追いかけて横切っていく。振る舞いがあまりに幼い様子だから、小川で足を取られてしまうような、森へ出かけそのまま行方が知れなくなってしまうような危うさがあるのだろうか。それとも、ほそやかな身体に不吉な出生の噂が絶えず付き纏うからだろうか。楽し気な様子のなかにどこか影を滲ませる。翠緑に見つめられると落ち着かなくなるのだと零す使用人も少なくない。本人が耳にしたならば、執着のなさがそうみせるのだろうと答えただろう。娘は均一にするのではなく、光と影、生と死、本物と偽物、そうやって分断している。すべてが借り物である。名前も、立場も、衣服も、寝台も、生命も、感情も、すべて。――いつか、返さなければならないことを識っている。ただ、神さまと別たれる日を想うと過る気配に、名づけることができないのだけれど。
ある日のことb:王室の政略結婚について意見を求められた
(敷地の片隅に佇むガラスで造られた鳥籠状のオランジェリーは20年前に王が側室へ贈ったものである。中央には噴水が置かれ、周囲は四季折々の植物が囲む。鳥が囀り、蝶が羽ばたき、色とりどりの光が天上から差し込む箱庭の在り方を外から覗き見ることは適わない。出身身分の低い寵姫への真綿で包むような深い情愛が滲む温室は、亡き妃の面影を宿す忘れ形見へと受け継がれた。いわくつきの姫君を主として頂く温室は誰をもの侵入を拒むことはなかったがわざわざ訪れるものは限られている。)……お母さま、ごきげんよう。(大理石で組まれた噴水のへりに腰掛け、足で水を跳ね上げながら花冠を編んでいた少女は、眠りから覚めたばかりのような舌足らずな口調で挨拶を来客へ返した。それっきり、微笑みのかたちのまま口を噤む。たくし上げたアイボリーホワイトのドレスの裾を窘められれば、風で足を乾かしながらくるりと反対へと向きをかえた。転がったハイヒールを履くことはせず、花冠を膝に乗せる。流れ落ちる水音とともに母の言葉へと耳を傾けていたものだけれど、)せいりゃく、けっこん?(大きく目をしばたかせ、世界の裏側にある呪文のように繰り返した。国の施策どころか、父王の思惑ですら与り知らぬところにある少女である。そのことを十分に傍らに腰掛けた美しいひとも知っているはず。だというのに、やわらかく微笑みながらも答えを促してくる。)…わざわざ会いにいらした理由、ね?(継母とは不仲という訳ではなかったが数多ある兄弟たちのなかで特別近しいという訳でもない。父母と食卓を囲むことはあれども二人きりで顔を突き合わせたことはない。)わたしが喜んだり、楽しめたり、できるようになる、ということ。(逡巡は扉が開かないことを確かめた視線が動くだけのわずかなうち。籠へ摘んだ花々のなかから一輪の赤々とした薔薇を取り上げて、策略や駆け引きとは無縁の、恋に恋する乙女のかおで打ち明けた。)塩を含んだ水が広がるうなばらや雲の中に住まうひとびとを見てみたいと思っているの。(主語は変わらず“I”のまま。しかし、言葉尻に少しだけ、この場にいないひとの存在を滲ませた。鮮烈で気高い、薔薇のようなひとを。別段、他人事という訳でもない。ただ、この瞳が映すことはないと判っているだけ。白い指先が瑞々しい花弁をなぞり、)陸と空のさかいを目指して馬で駆けたり、月夜にしか咲かない花を探して山を登ったり、ここに居ては出来ないけれど、よその国であればできる、かもしれないでしょう?(寝台のなかで交わした“いつか”の物語。天蓋では足りぬと布団を幾重にも被って、ひろげた御伽噺をわたし以外に教えたと知れば、怒るだろうか。怒るに違いない。怒りと哀しみを担うひと。とても優しいひと。ななしの神さま。)ふふ、お姉さまたちよりも、美しい花嫁になるのは確かなことよ。だからね、周りに笑顔があふれますように、皆が祝福してくれますように、優しいものでありますように……そう、…わたしは…ねがいます。(質問の意図とは異なることを知りながら、しかしこころの内側を浚ってもそれ以外の答えはない。喜びと楽しみを与えられた娘は言祝ぎを紡ぐと薔薇にカスミ草を添え、母へと預けた。かのひとは娘を百合と喩えたけれど、花であれば薔薇とともに飾られるものでありたかったとは伝えられないまま。)お母さま、明日も同じことを、わたしに訊いてくださいな。それで答えがひとつになるわ。(嫁ぐのであれば、それは“レティーシャ”である。この身がどこへ向かうとも、国の先行きに何の関わりもない事柄。)あ、お父さまとご一緒に、ね。(花を受け取った継母は返礼の代わりに娘のまろい額へと唇をよせ、やさしく肩を抱き寄せた。たおやかな所作で離れるとそのままその花園を後にする。――振り返らないひとの背を見送った娘の肩に頭上を羽ばたく鳥の影が落ちる。むせかえるような花の甘い香り、すずやかな水のせせらぎ、うつくしいものだけに囲まれて在ることをひとはしあわせと呼ぶのだろうか。)
捨てられてしまった赤い薔薇、真夜中の墓地に生い茂る刺草の糸、
片方だけ遺された耳飾り、そういうものを。
あなたは、しっている?